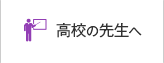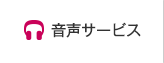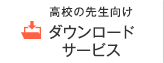- 美誠社ホーム
- > 英語研究室
- > A Little Grammar Goes a Long Way
- > 所有変化構文をめぐって(中)
英語研究室
※当サイトに掲載されている内容の無断転載を禁じます。
- 31
所有変化構文をめぐって(中)
2.1.2. for 型動詞の場合 しかし,(22)(イ)のfor型動詞の場合には方言差や個人差があるようです。 アメリカ英語では,IOを受け身文の主語にすることは,通例,容認されません (Fillmore 1965; Emonds 1976, pp.78-79, fn. 10; Huddleston 1984, p.199; Stowell 1981, pp.325-326; Celce-Murcia and Larsen-Freeman 1991, p.373; Goldberg 1992, p.53)。次の文法性判断はPinker (1989, pp.221-222)のものです。
方言や個人によりfor型動詞のIOを受け身文の主語にすることが容認されることもあるようです。 Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999, p.379, Endnote 12)は次の (25)はたいていのアメリカ英語の話し手には容認されないが,イギリス英語の話し手には容認されると述べています。
Allerton (1978, p.31)も次の(26), (27), その他の例をあげ,for型動詞のIOを受け 身文の主語にすることも可能としています。
イギリス英語の話し手であるEastwood (1994, §108.3)は,次の(28)aを,また, Swan (1995, §108.3)は次の(28)bをOKとしています。
また,Goldsmith (1980, p.447)は次の(29)a, bにはほとんど差が感じられないと言っています。
Huddleston (197l, pp.90-9l)は,for型動詞のIOの受け身の可能性は個々の動詞によっても変わると述べています。 たとえば次の(30)の容認可能性には個人差が出てくると言っています。
(28)bと(30)に対してはアメリカ人である元同僚のQuackenbush氏もOKと判断されます。 Alexander(1988, §1.13.3)は,for型動詞のうち,bringとbuyだけはIOの受け身がOKであると判断しています。 また,同じ動詞giveでも意味の違いによってIOの受け身を容認するケースと容認しないケースがあるようです。 次の(31)には(ア)「ジョンが私にある考えを教えてくれた」という意味と(イ)「ジョンを見て私がある考えをもった」という意味の2つがあります。
つまり,(31)のJohnは(ア)意図をもった動作主と(イ)原因の2つの意味役割で解釈できるということです。次の(32)はどうでしょう。
人間や他の高等動物以外のものが意図をもった動作主になることはできませんから,(32)のJohn's behaviorは(イ)原因の意味しかもつことができません。 IO が受動文の主語になるかどうかは主語が意図をもった動作主か単なる原因かに左右されます。 Emonds (1985, p.190)は,次の(33)と(34)を比較し,主語が意図をもった動作主のときには動詞giveのIOを受け身文の主語にすることは可能だが,主語が単なる原因のときにはの不可能だと述べています。
さらに,Stowell (1981, p.326)は,動詞begrudgeやcostのIOを受け身文の主語にすることはどの方言でも許されないと述べています。
ところで,初期の生成文法では受動変形(passive transformation)は意味から独立した統語規則の代表のように言われていました。 というのは,受動変形は,文が,統語上,次の(37)のフレームに入れば,動詞や動詞直後に現れる名詞句の意味にかかわらず,左から数えて第4項の名詞句を主語の位置に移動することが可能だと考えられていたからです。
(ただし,NPは名詞句(Noun Phrase),ZとYは変項(variable),Vxはある特徴をもつ動詞のクラスを表します。 変項のZとYの位置にはどのような記号列stringが来てもかまいませんし,何もなくてもかまいません。) たとえば,次の(38)a-eは,動詞と動詞直後の名詞句の意味は多様ですが,どれも(37)のフレームに入りますので,動詞直後の名詞句の主語位置への移動が可能です(Chomsky 1973, p.233)。
興味深いことに,(38)eの動詞expectと直後の名詞句the foodは異なる節に含まれており,それらの間には意味上何の関係もありません。 しかし,本節で見てきた事実は,受け身文をつくる操作が意味から完全に独立し,構造依存(structure-dependent)であるとする仮説に大きな疑義を投げかけています。 また,次の(39)a, bのコントラスト(Huddleston 1971,p.94)も構造以外の要因が絡んでいることを示唆しています。
次に,動詞に遠いほうの目的語DOの受け身を見てみましょう。
また,Stowell (1981, p.325)はほとんどの方言で次の(41)a-cの文は非文法的であると述べています。
Jaeggli (1986, p.596)もDOが受け身文の主語になることはほとんどの方言で容認されないと述べています。 Dryer(1986, p.811 fn.6, p.832 fn.23)は,DOが受け身文の主語になることを容認する人もいるが,自分を含めてほとんどの人が容認しないと述べています。 方言差を明示して,アメリカ英語では容認されないと述べる者もいます(Emonds 1976,p.190; Quirk et al. 1985, §2.21 Note [b]; Goldberg 1992, p.71, Note 4)。 容認不可能というわけではないが自然ではないと判断する者もいます。たとえば Quirk et a1. (1985, §16.55)は次の(42)の2つの文を比べてaのほうがbより普通だと言っています。
Huddleston (1984, p.196)も容認する人がいると述べています。 Jaeggli (1986, p.596)はIOが人称代名詞であればDOを受け身文の主語にすることが容認されると述べています。Frank(1972, p.56)の(43)の記述やSwan (1995, §410) の(44)の記述はJaeggliの主張を支持していると考えられます。
次の(45)の実例もIOが人称代名詞です。
Radford (1988, p.427)は次の(46)の規定を設けています。 (46)動詞に隣接している名詞句が受動文の主語になる。 (46)の規定は大部分の方言をカバーします。 おもしろい事実もあります。Northern British Englishでは次の(47)が容認されるそうですが,この文は(46)の隣接性の条件を満たしていないように見えます。
しかし,実は,この方言では「S+V+DO+IO」の語順が使われているのです。つまり,(47)では隣接性の条件が満たされているのです(Radford 1988, p.427)。 Radfordの規定を伝統的な文法用語を使って表現すると,「第3文型の目的語と第4文型の間接目的語が受動文の主語になる」となりますが,Radfordの規定のほうがより一般的なとらえ方をしていることは明白です。 ここで,多くの学習英文法書に見られる誤解を1つ正しておきたいと思います。たとえば,いつも私の机の上にある学習英文法書の1つであるMurphy(1994, p.86)は,次の(48), (49)a, bの例をあげ,所有変化構文は目的語が2つあるので,受動態の文が 2つできると述べています。
Thomson and Martinet (1986, §303C), Eastwood (1994, §108.1), Sinclair et al.(ed.) (1990, §10.20), Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999, pp.371-372)も同じことを述べています。 日本の出版社から出版されている多くの学習英文法書もそうです。しかし,受動文(49)aは能動文(48)から出てきますが,受動文(49)bは 出てきません。 the policeの前の前置詞toはどこから出てきたのでしょうか。 受動文は,能動文の主語を消し(あるいは,byに先導される前置詞句に変え,後ろに回し),能動文の目的語を主語に変え,動詞の部分を「be+過去分詞」 に変えますが,関係ないところに勝手に前置詞を入れたりはできません。 (49)bは次の(50)の受動文です(Huddleston (1984, p.196)も参照)。
学生には,(49)bが,(48)ではなく,(50)から出てくるということを理解してほしいと思います。 2.2.2. for 型動詞の場合 Fillmore (1965)はto型動詞の場合にはDOが受け身文の主語になることが容認されるが,for型動詞の場合には容認されないと述べています。
Huddleston (1971, p.97)はto型動詞を含む次の(52)は容認される可能性があるが,for型動詞を含む次の(53)a, bは非文法的だと主張しています。
Quirk et al. (1985, §2.21)は次の(54)の文を非文法的と判断していますが,これらの例で用いられている動詞はどれもfor型動詞であることに着目してください。
for型動詞の場合にはDOを受け身文の主語にすることは許されないと考えてよいと思います。 2.2.3. 対応する位置変化構文がない動詞の場合 この場合もDOが受動態の文の主語になることは許されません(Huddleston 1971, p.97)。
来月号に続きます。 大阪大学教授 岡田伸夫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||