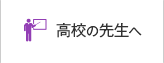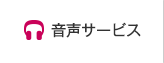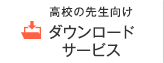英語研究室
※当サイトに掲載されている内容の無断転載を禁じます。
- 28
He ran too fast for me to keep up with him.のhimは省略しなくてもいいのでしょうか。(下)
前回は,
という質問に対して,日本の伝統的な学習英文法における記述を紹介し,正しい事実を示し,実例をあげました。今回は,近年の生成英文法研究や語法研究の成 果を考慮に入れ,さらに考察を深めたいと思います。読者の皆さんに理論的な英文法研究の一端を実感していただければ幸いです。 IV. 近年の科学的な英文法の論文や書籍における記述 伝統的な学習文法書が規則2を教えるのに対して,科学的な文法研究書は,次の(23)-(25)のような例をあげ,規則3を正しいとしています。
精密な語法研究で定評のある河上道生先生は,河上(1996, pp.365-367)の中で,ある英語参考書が,次の(27)と(28)を取り上げ,「(27)においては,文末のhimを省略することはできない。逆に(28)においては,readの後にitを入れると誤りになる。」と記述しているのを取り上げ,「上の記述は独断的であり,事実と合致しない。不定詞の前にfor ... があると,代名詞を入れることを許す傾向がある。(27)ではhimを省き,(28)では it を入れることができる。」と述べています。
V. for句のステータス しかし,(26)の規則3は中途半端です。なぜそのような規則が存在するのか何も説明していません。これからその説明に取り掛かりますが,ステップを踏んで考えていけば,それほどむずかしいことではありません。 まず,for句には主節の述語にかかるものと,to不定詞の主語として機能するものの2つがあるということを見ておきましょう。次の(29)を見てください。
for the richはpleasantにかかり,for the poor immigrantsはto do the hard workの主語です。その証拠にfor the richは文頭や文末に動かすことができます。
次の(32)ではfor句がto不定詞の主語になっています。
それに対して,次の(33)ではfor句はdifficultにかかっています。
上の(23)の文は次の2通りに分析することができます。
もちろんfor句の中に現れる要素がthere構文のthereのときには,これが主節の述語を修飾することはありえないので,to不定詞の主語としてしか解釈できません。したがってfor thereを文頭や文末に動かすこともできません。
では,(34)と(35)の違いをどのように説明すればよいのでしょうか。so ... that ... 構文のthat節の中に出てくる主節の主語や目的語と同じものを指す代名詞を省略することはできないというよく知られている事実をとっかかりにするといいと思います。一般的に現在あるいは過去の時制をもつ定形節(that節がそうです)の中の要素は,主語であろうと,動詞の目的語であろうと,主節の主語や目的語と同一人物を指していても省略することはできません。
so ... that ... 構文の場合,that以下は1つの従属節をなしています。だからso ... that ... 構文のthat節中の代名詞を省略することはできないのです。 さて,いよいよtoo ... for ... to ... 構文です。何もむずかしいことはありません。「(23)を(34)のように分析したら代名詞の it は必ず省略する。それに対して,(23)を(35)のように分析したら代名詞は省略しない。」それだけのことなのです。次にこのことを規則4として述べておきましょう。
次に,規則4が正しいことを見てみましょう。次の(40)ではsolveの目的語が,また,(41)ではforの目的語が顕在しています。
この場合には,for句は,to不定詞の主語なのですから,文頭や文末に動かすことはできません(Lasnik and Fiengo 1974 pp.538, 556)。
逆に,代名詞がなければfor句は主節の述語の修飾語なのですから文頭や文末に動かすことができます。
VI. 進んだ考察 次に2つばかり少し進んだ内容を取り上げます。まず,最初にあげるのは主節の要素とto不定詞の中の目的語の間の距離です。一般的に,too ... for ... to ... 構文で,主文の主語とto不定詞の代名詞が距離的に近いと受け入れられる可能性が低下し,逆に,その2つの距離が広がると,受け入れられやすくなります(Ross 1967a, p228; 荒木1986, pp. 441-442)。次の例文がいいかどうかの判定はRossのものです。 (46)と(49)の英文の文頭の?はこの英文が文法的と非文法的のボーダーライン上にあることを標示します。
これはある意味で常識にかなった判断のように思われます。主節の主語と,to不定詞の顕在しない(あるいは透明の)目的語の間の距離が広がると,顕在しない目的語が,前に出てきた主節の主語と同じものであるということがわかりにくくなり,そのことを避けるために代名詞を入れることが好まれるのでしょう。 2番目の点ですが,私のインフォーマント(ミシガン大学言語学Ph.D)は,次の(50)の2つの文で,代名詞のitやthemはあってもなくてもよいと判断します。
for thereは主節のsmallとかstupidにかかるものではなく,to不定詞の主語です。そのことは,次の(51)a, bが非文法的であることからもわかります。
このあたりになると何が事実かなかなか簡単には決められなくなります。私のもう1人のインフォーマント(大阪大学外国人教師のイギリス人)は,(50)aは代名詞のitがあってもなくても文法的,(50)bはthemがあれば文法的だが,themがないと非文法的と判断します。上の(50)a, bでitやthemを省略することができるという前提の上での話ですが,(39)の規則4は成立しないということになります。そして残るのは(26)の規則3ということになります。 しかし,規則3は極めて不自然です。なぜ「to不定詞の前にfor ... が顕在している場合」という条件が課せられるのか,その意味がわかりません。for句には主節の述語を修飾するものとto不定詞の主語となるものの2つがあり,この2つは別物です。それにもかかわらず,どうして「to不定詞の前にfor ... が顕在している場合」というまとめ方ができるのでしょうか。そのように考えてくると,次の規則5が候補として浮かび上がってきます。
実は規則5はそれほど奇妙な規則ではありません。that節は顕在的な主語を含み,さらに,主動詞あるいは助動詞の部分に現在あるいは過去の標示がつきます。したがって,次の(53)に見られるように,従属節であることを合図するthatを除けばそのまま主節として成立します。
それに対して,to不定詞は節に必要な主語や現在あるいは過去の標示を欠くのでそのまま主節になることができません。for ... to ... 節は,単独のto不定詞に比べると,主語となるfor句を含んでいるという点でthat節に近いのですが,現在あるいは過去の標示を欠くのでやはり単独で主節として成立することができません。この段階的違いを図示すると次の(54)になります。
つまり規則5は,節としての完成度に関してfor ... to ... 節がthat節とto不定詞の中間に位置するということにその動機づけがあると思われます。ただし,ここの話はすべて上の(50)a, bにおいて代名詞のitやthemを省略することができるという前提での話です。もし事実をもっと広範に調べて(50)a, bにおいて代名詞のitやthemを省略することができないという結論が出れば,(39)の規則4が正しいと考えていいことになります。 さて,以上,too ... for ... to ... 構文におけるto不定詞あるいは前置詞の目的語が出てくるか省略されるかについて詳しく見てきましたが,(15)の規則2が 正しいと誤解していた場合にはどのようなことが起こるのでしょうか。英語を話したり,書いたりする(発信する)ときには,正しい形をつくることができま す。代名詞が顕在する形をつくれないという点では表現の多様性が落ちますが,間違った形はつくらないわけですから,それほど大きな問題にはならないでしょ う。英語を聞いたり,読んだりするときにはどうなるでしょうか。規則2をしっかり覚えていればいるだけ,(16)-(22)のような生の英語に触れたときに戸惑うかもしれません。その意味では(39)の規則4あるいは(52)の規則5を覚えたほうがいいでしょう。
最後までお読みいただき,ありがとうございました。 References Alexander, L. G. (1988) Longman English Grammar, Longman, Harlow. 荒木一雄編 (1986)『英語正誤辞典』研究社出版. Chomsky, Noam (1977) Essays on Form and Interpretation, Elsevier North-Holland, New York. Close, R. A. (1975) A Reference Grammar for Students of English, Longman, Harlow. 河上道生 (1996)『英語参考書の誤りとその原因をつく』4版, 大修館書店. Lasnik, Howard and Robert Fiengo. (1974) “Complement object deletion,” Linguistic Inquiry 5, 535-571. LDOCE (2003)=Longman Dictionary of Contemporary English, 4th ed., Pearson Education, Harlow. Murphy, Raymond (1994) English Grammar in Use, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, London. Rosenbaum, Peter S. (1967) The Grammar of English Predicate Complement Constructions, MIT Press, Cambridge, MA. Thomson, A. J. and A. V. Martinet (1986) A Practical English Grammar,4th ed., Oxford University Press, Oxford. 大阪大学教授 岡田伸夫 2005年2月28日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||